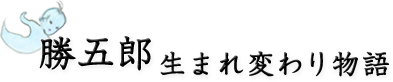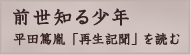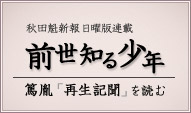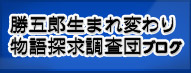簗瀬均氏、秋田魁新報社の許可を得て掲載しています。大きな画像はこちら
氏神の神事を行えば、災難に遭わないと篤胤(あつたね)は考えた。
中世から伝わる昔あったことを紹介しよう。『古今著聞集(ここんちょもんじゅう…鎌倉中期の説話集)』に次のような話がある。
吉田神社は藤原氏の氏神だ。仁安(にんあん)3(1168)年4月21日、吉田祭りの日、伊予守藤原信隆朝臣(後鳥羽天皇の外祖父)は氏子なのに神事をせず、仁王講(にんのうこう)を行っていた。すると常夜灯(一晩中ともしておく明かり)の火が、障子に移って自宅が焼けた。
隣に同じ氏子の民部卿(みんぶきょう)藤原光忠の家があったが、神事を行っていたためか延焼を逃れた。大炊御門(おおいのみかど)室町(京都市)での出来事だ。神威(しんい…神の威力)恐るべきだ。
藤原氏の氏神・奈良の春日大社を勧請したのが、京都にある吉田神社だ。藤原信隆は吉田神社の神事をしないで、「仁王講」という「仁王般若経(仏教経典)」を読経する法会(ほうえ)を行ったため自宅が焼けた。一方隣の藤原光忠は吉田神社の神事を行ったので延焼を逃れたと篤胤は判断する。
「仁王般若経」は、災難をなくし幸福を得ると説く仏の教えだ。それなのに藤原信隆は火事に遭った。篤胤は仏事よりも、氏神の神事を優先すべきだったと考える。
また藤原重澄は若いころ、兵衛尉(ひょうえのじょう…兵衛府の判官)という官職に就きたいと願い、稲荷神社(産土の神)の氏子でありながら、他の土地にある賀茂神社に奉仕し土蔵まで造って献上した。
稲荷は『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』にある「山城国紀伊郡(京都市伏見区)の御社(伏見稲荷大社)」をいう。賀茂神社は「愛宕郡(おたぎのこおり)(京都市北区)の賀茂別雷(かもわけいかづち)神社」だ。
重澄は兵衛尉になりたくてあちこちに手を回し、社家(神主)に推挙されていたから、外れるはずはなかったが、たびたび除目(じもく…任官の儀式)で選ばれなかった。重澄は祈祷師に言いつけて任官されるよう祈願してもらった。すると祈祷師が次のような夢を見た…。
稲荷大明神から使者が訪れた。用件を聞くと使者がこう告げた。「重澄の願いは絶対に聞き届けられない。重澄は我が膝元に生まれながら、我を忘れている(産土の神を差し置き、他の土地の神を信仰している)」と。
こうして稲荷大明神の言葉を使者が伝える形で、祈祷師との問答が繰り返された。「そういうことで今回は重澄を除目から落として思い知らせ、次回の除目を…」と言って稲荷大明神の使者は帰った。
祈祷師は驚き、急いで重澄のもとへ駆けつけ、この夢の内容を報告した。真偽を怪しんでいたところ、果たして次の除目でも任官されなかった。
重澄が夢の真偽を確かめようと、稲荷神社へ参拝すると、特に働き掛けなかったが、次の除目ですんなりと任官された。こうした話は、いろいろな書物に見られる。
重澄は産土の神を忘れ、他の土地の神を熱心に信仰していた。それが希望する官職に就けない要因となった。だが産土の神に参拝したところ、すぐに任官されたという。
このように鎮守の神や氏神などが、その所々の人々を分担して守っていることを自覚すべきだ。
寛平7(895)年12月3日の官符(太政官が諸国に下した公文書)に「人々の氏神のほとんどが畿内にある。毎年2、4、11月の先祖の祭りをなぜ、なくそうとするのか。もしも従来通り行おうとする者がいれば、すぐに祭りを強制する官宣(太政官から諸社寺への公文書)を下そう」とある。氏神の祭りを勧め、産土の神も大切にすべきだ。
篤胤は、身近な神への信仰を力説する。