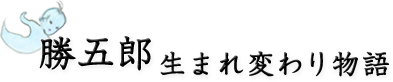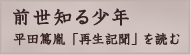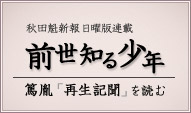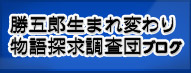簗瀬均氏、秋田魁新報社の許可を得て掲載しています。大きな画像はこちら
平田篤胤著『再生記聞』には、勝五郎の前世である藤蔵は死後しばらく家にいたが、やがて見知らぬ老人に誘われて奇麗な草原へ旅立ったと記述されている。
松浦静山の『甲子夜話』では、藤蔵と主に関わったのが地蔵菩薩(じぞうぼさつ)だった。『江戸名所図会』の著作で知られる考証家の斉藤月岑(さいとう・げっしん…1804~1878年)の『睡余操觚(すいよそうこ)』にも地蔵菩薩が登場する。
情報屋のはしりとされる須藤由蔵(すどう・よしぞう…1793~没年不詳)の『藤岡屋日記』の文政7(1824)年7月28日には「小児前世を忘れず居ること」があり、そこでは出家せず、家庭にあって仏道修行に励む「優婆塞(うばそく)」のような白髪の老人が現れる。
同日記には「勝五郎の家を訪問すると、父母や兄姉までいたので質問した」とあり、勝五郎の家族と直接面会して書いたことがうかがえる。
死後の記憶の描写には、自分の家に対する特別な思いが薄らいでいく心情面の変容も垣間見られる。
「おらは棺(ひつぎ)の上にいて墓まで行ったが、また家に帰って来た。でも生きていた時とは違って、わが家に寄せる親しみが薄らいでいた。そういうことで家を去り、村から見渡す山々の峰の、松のもとに着いた時、優婆塞のような白髪の老人が、灰色の袖の長い衣を着てやって来た。そしておらに向かって言った。『おまえは、わしと一緒に来なさい』。それから老人に伴って地を走り、あるいは中空を飛んだ ~中略~ また家々で火をたく時はわが家に帰った。(家々で火をたく時とは、7月の迎え火)」(『藤岡屋日記』より)
「火をたく時」を、お盆の迎え火と捉えている。『藤岡屋日記』では、わが国の一般庶民が行っている仏教行事と関連させながら、優婆塞のような白髪の老人が藤蔵を誘っている。
優婆塞は在家の僧だが、山岳で修行し、時には呪術を身に付けたといわれており、藤蔵を導く存在にもなり得たのだろうか。(参考『鈴屋学会報』第28号「勝五郎再生記聞小考 門脇大」2012年12月)
さて『再生記聞』では、老人に誘われた藤蔵が奇麗な草原で遊んでいると、烏(からす)が現れて驚かされる。
花がたくさん咲いているところで遊んでいた時、その枝を折ろうとすると、小さい烏が出てきて、大変驚かされたのを、今でも怖ろしく思い出す。
(「その老人は中野村の産土神(うぶすながみ)である熊野権現だろう」と父源蔵が語った。烏が出たことについては、何となく思い当たる節がある)。※伴信友の注釈
産土神とは、生まれた土地の守り神。生前から死後まで、その人が他所に移住しても生涯守護する神だ。
篤胤が唱える幽冥界(ゆうめいかい…あの世)の主宰者には大国主命(おおくにぬしのみこと)がいて各地のことは、その土地の国魂神(くにたまのかみ…国土の神霊)、一宮の神(地域で最も社格の高い神)や産土神・氏神が関わると考えた。だから篤胤や親友の伴信友は、勝五郎の父源蔵の発言にうなずいて、藤蔵が出会った老人は産土神だろうと判断したようだ。藤蔵が勝五郎として生まれ変わった武蔵国多摩郡中野村(東京都八王子市東中野)の産土神は、熊野権現であった。
こうして篤胤の幽冥論は、勝五郎の事例によって裏付けられ、確かなものになっていく。このように篤胤には、初めから自分が考える「神々の全体像」があり、さまざまな事例を基に総合的に判断し、理解していこうとする傾向が見られる。
宗教学者の山折哲雄氏は、「カミの表現が老人をモデルにしているのに対して、ホトケの表現が中・青年をモデルにしている」と述べている。つまり神は老人の姿をし、仏は中年や青年の姿をしているという。
人間が死んだ後、神になると、私たちの先祖は古くから自然に信じてきた。三十三回忌ないしは五十回忌の弔い上げが済んだ死者の霊は、個性を失って祖霊(祖先の霊)になり、やがて年月を経て神に祀(まつ)られるという。
自然の摂理である死において、死とそれほど遠くない「老人」という存在が、生きている者と死んだ者の「中間」に位置すると考えられた。つまり老人は神に近い存在なので、神の像が老人の姿になったのではないか、と山折氏は考えた。(山折哲雄『神と仏-日本人の宗教観』、講談社、1983年)